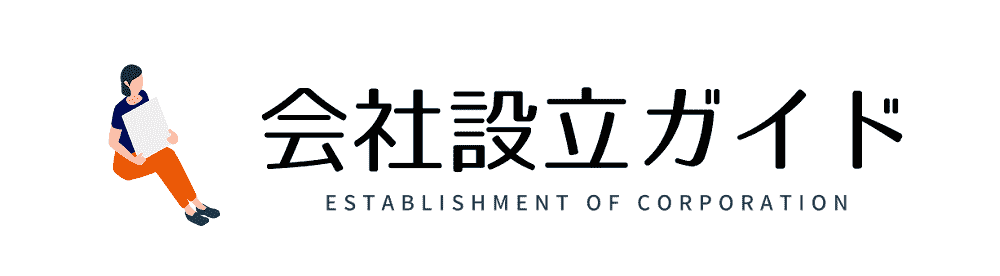納税関係の書類の、
所得税徴収高計算書
について、どんな内容の書類なのかを知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
税務署に提出する「所得税徴収高計算書」の内容について、わかりやすく説明しています。

会社を設立した後、法人が支払う税金としは、下記があります。
・法人税
・地方法人税
・法人住民税
・法人事業税
・固定資産税
・社員から源泉徴収した所得税
・社員から源泉徴収した住民税
・事業所税
・消費税
まさに、重税国家という感じがしなくもありません。
松下幸之助さんが、生前おっしゃられていた、「無税国家」が実現していたら、どんなに楽だったかと想像してしまいます。
(無税国家に関心のある方は、本ページの最後にリンクをつけています。)
もっとも、
源泉徴収した金額や消費税
は、単に、預かり分ですので、法人に対する直接的な税金ではありません。
さて、社員から源泉徴収した所得税については、税務署から送られてくる、
「所得税徴収高計算書」
という書面に必要事項を記入して、銀行などで支払いを行います。
内容について、下記に順に説明していきます。
(参考)[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
社員から源泉徴収した所得税の支払いタイミング

社員から源泉徴収した所得税を支払うタイミングは、2つのパターンがあります。
パターンの違いは、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しているかどうか
によって変わってきます。
但し、この特例は、
従業員が10人未満の場合の特例
となります。
結論からいうと、従業員が10人未満の場合は、提出しておいたほうが良いです。
具体的には、下記の違いになります。
■申請書を提出している場合
・1月から6月までの所得分 → 7月 10 日までに納付
・7月から 12 月までの所得分 → 翌年の1月 20 日までに納付
■申請書を提出していない場合
徴収した月の翌月(毎月)
毎月だと手間が面倒ですね。
また、注意点としては、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する際、翌月末の承認
になります。
例えば、
6月10日に申請書を提出した場合
には、
その手続きが、7月からの適応になってしまいますので、6月分の給与があれば、翌月に所得税をおさめる必要がある
ことになってしまいます。
私の場合も、申請月の分を納めてなかったので、わざわざ、税務署の職員から電話がかかってきました。
ひとつひとつチェックしている人がいるのですね、ご苦労様です。
記入のしかた

国税庁から下記のような書面が送られてきます。
これに手書きで数字を記入します。
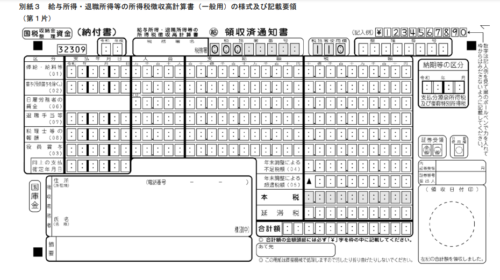
ちなみに、この用紙は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
の提出の有無で、書面の種類が異なります。
申請書提出している場合は、
年2回の提出なので、期間指定(令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日)での記載の仕方
になっています。
それぞれの項目を記載します。
1.年度
2.税務署名
3.整理番号(税務署から割り振られている整理番号)
4.納期等の区分(給与の支払い年月を4桁の数字で記入)
5.俸給・給料等
6.本税:(各項目の税金の合計)
7.合計額:(延滞税分がない場合は、本税と同額に)
8.徴収義務者:(事業主の住所と名称)
記載方法について、国税庁のサイトは、下記になります。
正直、わかりづらいです。
(参考)改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
(参考)納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)(国税庁) (PDF)
記入の仕方についての参考サイト

下記のサイトも参考になります。
所得税徴収高計算書の記入方式(マネーフォワード)
開業に必要な源泉所得税の「納期の特例」とは?申請書の書き方(マネーフォワード)
所得税徴収高計算書とは?記入方法と納付方法(Square)
補足

参考;松下幸之助が考えた国のかたち 「無税国家」「収益分配国家」への挑戦 Kindle版
無税国家という発想が素晴らしいです。
多分、運用次第では実現できるのでしょう。
松下政経塾出身の現在の政治家の様子を見て、天国の松下幸之助さんは、何を思うのでしょうか。

松下幸之助が考えた国のかたち 「無税国家」「収益分配国家」への挑戦
以上、所得税徴収高計算書とは?(社員から源泉徴収した所得税)についての説明でした。