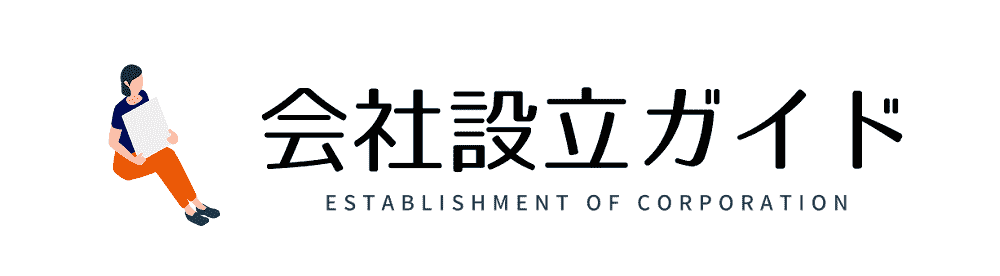会社設立の際に、
費用がどれくらいかかるのか?
について知りたい
こんなテーマに関する記事です。
会社を設立する時の費用について、わかりやすく解説しています。

会社の設立を検討する際には、
・会社設立の際にかかる費用
がどれくらいかかるのかも把握しておく必要があります。
下記に順に説明していきます。
会社運営にかかる費用について

法人を設立した後は、
・設立時に発生する費用
・会社運営の中で継続的に必要をなる費用
があります。
それらも事前に念頭においておくと良いでしょう。
設立時に発生する費用
これは、
・法人登記をする為の費用
・定款認証の為の費用
・法人の印鑑購入の為の費用
の他、
・司法書士さんや、行政書士さんに依頼する場合は、その為の手数料
が必要となります。
具体的な金額としては、概算、下記内容になります。
法人登記の費用
株式会社の場合
■公証役場
定款認証手数料 5万円(資本金によって異なります)
定款印紙代 4万円
定款謄本代 約2,000円
■法務局
登録免許税 15万円
登記事項証明書代 1通600円
印鑑証明代 1通450円
※定款認証手数料については、令和4年1月1日から変更になりました。
資本金の額毎に金額が異なります。
・資本金100万円未満;3万円
・資本金100万円以上300万円未満;4万円
・その他;5万円
合同会社の場合
■公証役場
定款印紙代 4万円
■法務局
登録免許税 6万円
登記事項証明書代 1通600円
印鑑証明代 1通450円
法人印
法人登記の書類を作成する時点で、
法人印
を用意しておく必要があります。
登記には実印のみでOKですが、通常は、
実印、銀行印、角印
をまとめて用意する場合が多いです。
価格的には、お店によって、また、材質によって価格差があります。
材質は、柘植や黒水牛の他、チタン製というものもあります。
好みと価格によっての検討です。(チタンの場合は、ちょっとお高めの金額になっています)
また、法人印については、下記ページに詳細を説明しています。
会社設立書類の作成

法務局等に提出する書類の作成については、
・司法書士さんや行政書士さんに依頼する
・自分で作成する
・クラウドサービス(マネーフォワードや弥生のかんたん会社設立)を利用する
の3つのパターンがあります。
司法書士さんや行政書士さんに依頼する場合は、手数料が発生します。
自分で作成する場合は、結構、手間がかかる上、電子定款を使用しない場合、4万円の実費は必要となります。
クラウドサービス(マネーフォワードや弥生のかんたん会社設立)を利用する場合は、書類作成費用自体は、無料なので、お勧めです。
電子定款費用については、
・弥生のかんたん会社設立;無料
・マネーフォワード;5,000円(マネーフォワード会計の利用で無料)
となります。
下記に順に説明していきます。
会社設立の手続きを「司法書士さんや、行政書士さん」に依頼する場合
法人設立の手続きを、司法書士さんや、行政書士さんに依頼する場合は、
登記にかかる費用(実費)
の他、
その事務所への手数料
が必要となります。
司法書士さん
司法書士さんの場合は、通常、
法務局等への書類の申請も代行してもらえる
ので、楽ではあります。
事務所への手数料については、事務所によって料金が異なりますが、相場としては、
10万円前後の場合
が多いようです。
(また、司法書士さんでは、通常、電子定款を利用しますので、通常の定款費用(4万円)の実費はかかりません)
行政書士さん
行政書士さんの場合は、書類作成のみのサービスなので、法務局等への提出は、自身で行う必要があります。
(行政書士さんとは、いわゆる「代書屋さん」のことになります)
料金については、事務所によって、かなりばらつきがあります。
司法書士さんや行政書士さんに依頼する場合
料金設定は、その事務所によって異なりますので、
サービス内容と費用
の点や、
場所的に近い先にするかどうか?
ネットでの対応の先にするかどうか?
などの条件での検討になります。
自身で対応する場合
この場合は、定款費用の問題がでてきます。
つまり、通常は、4万円の費用が発生しますが、電子定款にするとその費用が発生しません。
ただ、自身で
電子定款
を環境を整えると、それはそれで費用が発生します。
ですので、方法としては、
電子認証の対応をしている、低価格の行政書士さんに依頼する
や、あるいは、
マネーフォワード(電子定款費用は通常5,000円)や、弥生のかんたん会社設立(電子定款費用は無料)を利用する
などの選択肢が考えられます。
要注意!設立費用0円をアピールしている会社の場合
会社設立費用を0円で対応している先があります。
その場合、ほとんどが、会社設立の費用を0円にする代わりに、
何かの条件
がついています。
例えば、
会社設立後の税務顧問を条件にしている、
あるいは、
オフィス商材のリースを条件にしている
などです。
ですので、どんな条件がついているのかを必ず確認しましょう。
設立費用0円でも、条件によって、結局、高額な負担になる可能性があります。
【参考】会社設立後に継続的に必要となる費用について

会社設立後に継続的に発生する費用としては、下記のものがあります。
税金
法人が支払う税金は、下記の3つの種類があります。
「法人税」 ;国税
「法人住民税」;地方税
「法人事業税」;地方税
「法人税」;国税
会社の所得に対してかかる税金です。
ですので、赤字の場合は、法人税はかかってきません。
注意点としては、法人税の会社の所得に対する定義づけが、通常の会社の利益に対する定義と若干異なるという点です。
通常の会計では、
収益 − 費用 = 利益
となりますが、法人税の対象となる会社の所得は、
益金 − 損金 = 所得
となります。
ですので、損金計上できるかどうかの見解で、所得の金額がかわってくるということになります。
「法人住民税」;地方税(市町村)
これは、法人の事業所がある地方自治体(市町村)に対して支払われるものです。
一般個人に住民税があるように、
法人も、人格をもっている
という法的解釈があるためなのか、住民税を支払う必要があります。
会社が赤字の場合でも、最低、年間7万円程度は支払う必要があります。
「法人事業税」;地方税(都道府県)
これは、都道府県に支払う税金になります。
これは、「所得」に法人事業税率を乗じて算出しますので、赤字の場合は、ゼロになります。
ここでは、法人税は、赤字の場合でも最低限、7万円程度の費用が発生するということをおさえておきましょう。
社会保険の費用について
会社員の場合は、社会保険費用の半分を会社が負担していました。
ですが、自身で会社を設立した際は、
自身の会社で半分の負担
残り半分を自身の給与の中から負担
ということになります。
また、社員を採用した際は、
会社で、社会保険費用の約半分を負担
することとなり、これは、会社が赤字の場合でも、その負担は変りません。
会計処理と、決算申告について
会計処理と決算申告について、税理士さんに依頼する場合、その費用が発生します。
帳簿づけ(記帳)などの会計処理に関しては、事業内容によっては、会計ソフトなどを使用して対応できる場合もあります。
最近は、クラウド会計も使いやすいものがでています。
ただ、事業内容によっては、会計処理がややこしいケースもあります。
その場合は、税理士さんに相談することになります。
実際、税理士さんの対応レベルや知識レベル、料金体系も、人によってかなり幅がありますので、その選定には、注意が必要です。
また、クラウド会計に対応していることを前面にアピールしている税理士さんもいますので、料金とも相談して検討すると良いでしょう。
さいごに

法人設立の注意点について記載しましたが、もちろん、下記にようなメリットもあります。
(状況よっては、デメリットを上回るだけのメリットもあると言えます。)
・法人のほうが取引先、顧客からの信用を得やすい
・金融機関からの融資が受けやすい
・税務申告の際に、経費として計上できる項目が多くなる
・有限責任となる(個人事業の場合は、その個人の無限責任となる)
以上、会社設立時の注意点についての説明でした。