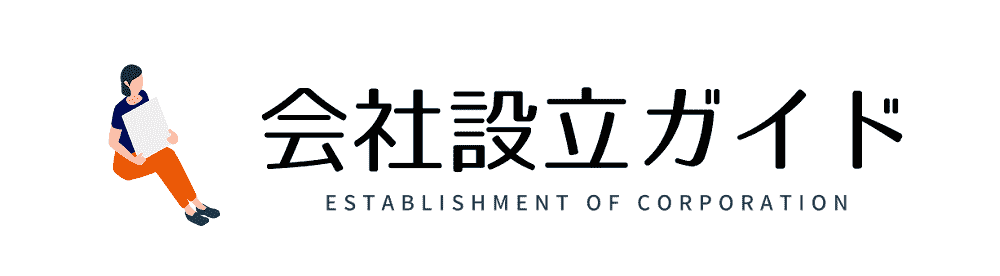事務所や店舗を借りる際の
注意点
があれば知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
事務所や店舗を賃貸して、事業をスタートする際に、注意すべきポイントについて整理しています。

会社を設立して、事務所や店舗を借りる際には、
テナント契約
をすることになります。
その際に、
・契約時
・更新時
・解約、退去時
といった時点でのお金がどれくらいかかるかの取り決めをします。
また、契約書自体
も、
普通借家契約
と
定期借家契約
の2種類の契約パターンがあります。
下記にそれぞれの注意点についてみていきましょう。
契約時に必要なお金

契約時には、通常、
・初月の賃料
・敷金もしくは、保証金
・諸経費(主に仲介手数料、火災保険[借家人賠償]、保証会社費用)
が必要となります。
これらのことは、契約前に、金額の妥当性をチェックすることになり、条件があえば、具体的な契約を検討することになります。
賃料について
賃料については、そのエリアの相場を調べて、判断します。
実際、物件によっては、相場よりかなり高い(強気)の家賃設定をしているケースもありますので、しっかりと調べるようにしましょう。
また、賃料について、値引き交渉が可能かどうかという点ですが、
値引き交渉が可能な場合
もあります。
結局、賃料設定に明確なルールはなく、通常は、周辺相場から判断して、物件のオーナーが、
妥当と思われる金額で賃料を設定
します。
ですので、例えば、長期間、空いているようなテナントの場合、価格交渉にも応じてくれる可能性もあります。
但し、注意点としては、
価格交渉する場合は、その条件が通ったら借りる前提
で行うということです。
値引き交渉をして、値引きできたとして、結局、借りないのであれば、意味のない行動となります。
意味の無いことは、控えたほうが賢明と言えます。
敷金もしくは、保証金
敷金あるいは、保証金には、決まったルールはありません。
テナントの場合は、
結構、高額になる可能性
があり、また、
条件(敷引きあるいは、敷金償却)が厳しい
場合があるので、要注意です。
敷引きあるいは、敷金償却とは、退去時に、基本、返却されるべき、
敷金、保証金が、差し引かれること
を言います。
これは、物件のオーナー(貸主)の都合によるものです。
敷引きあるいは、敷金償却がある場合、差し引かれる金額は、
賃貸借契約書
に記載がありますので、必ず、チェックしましょう。
契約を取り交わす前に、条件面をしっかりと確認するとともに、契約の取り交わしの際にも、場合によっては、
サラッと流すように説明されてしまうケース
もありますので、文言のひとつひとつをしっかりと確認することが大切になります
また、場合によって、敷金もしくは、保証金が高額で、
郊外の土地を買って、そこに、小さい事務所を建てたほうがいいのでは?
と思ってしまいような場合もあります。
少なくとも、敷金あるいは、保証金が、周辺相場に比べて高い物件は、避けたほうがよいでしょう。
また、敷金と保証金の違いは下記になります。
ただ、実質は、同じような意味合いになります。
敷金と保証金の違い
敷金;家賃などの債務の担保として貸主が預かるお金です。
退去の際には、基本、敷金から現状回復費用が差し引かれます。
保証金;家賃などの債務の担保や原状回復のための費用として預かるお金です。
敷金、保証金が高い理由のひとつは、
工事を伴う店舗の場合、借主は、退去時には現状回復を行うことになりますが、万が一、原状回復を行わなかった場合
のことを想定しているからになります。
その場合は、貸主は、敷金や保証金で現状回復工事を行うことになります。
諸経費
諸経費としては、主に、
仲介手数料
火災保険[借家人賠償]
保証会社費用
があります。
仲介手数料
仲介手数料は、
家賃の1カ月分+消費税
です。
これ以上の仲介手数料を支払う必要はありません。
それを超える仲介手数料は、宅建業法違反となります。
宅地建物取引業法 第46条4項目第四貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。
この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。
つまり、仲介する不動産会社は、賃貸の仲介手数料は、総額で、賃料の1カ月分+消費税になります。
ですので、ちょっと細かいお話しになりますが、仲介している不動産会社が、テナントオーナー(貸主)からも仲介手数料をとっている場合は、借主側の仲介手数料は、
賃料の半分 +消費税
が正解となります。
火災保険[借家人賠償]
その物件自体には、所有者が火災保険をかけていますが、テナントの借主も、
借家人賠償
という火災保険に入ります。
これは、そのテナントの契約年数の期間で契約して、テナント更新時には、同様に火災保険[借家人賠償]も契約することになります。
保険のプランや、テナントの広さ、構造にもよりますが、通常、金額的には、そう大きな金額ではありません。
保証会社費用
保証会社の保証は、
賃料の滞納があった場合に、家主への賃料を保証会社が賃料を立て替える
という仕組みになっています。
通常、賃料の1カ月分程度の費用になります。
この費用は、
テナントオーナーが負担する場合と、借主が負担する場合
があります。
しかしながら、結局、借主が負担する場合のほうが多いというのが実状です。
また、賃料の滞納があった場合、
家主への賃料を保証会社が賃料を立て替える
といっても、借主の負債がなくなる訳ではありません。
単に、
保証会社から借主に請求
がくるだけのお話しになります。
尚且つ、通常、請求費用に手数料が加算されることになります。
また、テナントオーナーな仲介する不動産会社によっては、
保証会社
を使っていない場合もあります。
更新時

契約の更新の際に発生するのが、
更新料
です。
これも、きまったルールはありません。
また、普通借家契約の場合、通常は、
契約期間が満了になった場合は、自動更新する
という内容の特約をいれます。
その際に、更新料が発生するというこになります。
ですので、
契約期間が1年の場合
は、毎年更新料が発生しますので、注意が必要です。
普通借家契約の契約期間が長いと、更新料の支払う頻度も少なくなります。
その場合の注意点としては、
契約の途中解約の際の特約
がどうなっているかを確認しましょう。
具体的には、
解約の際には、どれくらい前に通知をする必要があるのか?
と、
途中会社の際のペナルティーが設定されているかどうか?
になります。
契約条件をしっかりと確認しましょう。
解約、退去時

中途解約の際には、上記にも記載した内容で、
中途解約の際の条件
について、契約上の条件をチェックします。
また、契約満了に伴う解約の際にも、
事前に更新しない旨の通知
を行う必要があります。
解約、退去時のお金のことに関しては、敷金や、保証金に関して、
実際にどれだけ戻ってくるのか?
という点になります。
これは、住居の賃貸の場合と同じで、トラブルになりやすいポイントになります。
店舗などの場合、現状回復工事を行って退去することになります。
スケルトンの状態で借りた場合は、スケルトンの状態に戻します。
事務所使用の場合も同様に、借主に、現状回復義務があります。
民法では、
民法621条:賃借人の原状回復義務
で明文化されています。
「賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ)がある場合において、賃貸借契約が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」
民法621条:賃借人の原状回復義務
では、事務所などの賃貸で、スケルトン状態では無い場合は、現状回復の範囲はどうなるのでしょうか。
国交省のガイドラインでは、下記の記載となっています。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」
国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』より
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
つまり、通常使用により汚れ、損耗に関しては、
現状回復の対象に該当しない
という解釈になります。
但し、貸主側としては、退去後、新たな入居者を募集する際に、
クロスやカーペットなどの修繕工事
を行う為、その修繕工事の費用が発生します。
ですので、退去の際に、修繕を含めた現状回復工事の費用と、敷金や保証金の返却分から差し引くケースがあります。
こういったケースでトラブルになる可能性があります。
ここでの論点は、
通常損耗は、現状回復に該当するかどうか
という点になります。
住宅の場合は、通常損耗は、現状回復に該当しないというコンセンサスができています。
では、
テナント物件の場合
はどうなのでしょうか?
裁判所の判例としては、
平成12年12月27日東京高等裁判所判決
と
平成17年東京簡易裁判所判決
の2つが参考になります。
平成12年12月27日東京高等裁判所判決
平成12年12月27日東京高等裁判所判決では、
・原状回復工事は入居テナント側が負担する。
・通常損耗も含めて入居時の状態まで原状回復義務を負わせることは合理性がある。
という見解になっています。
つまり、通常損耗も、原状回復工事の対象になるということです。
但し、この判例の案件は、
テナントが比較的大規模で、原状回復工事も高額になる
という背景がありました。
平成17年東京簡易裁判所判決
逆に、
平成17年東京簡易裁判所判決
では、テナントが小規模なケースで、
通常損耗は、現状回復の対象にはならない
という見解が提示されています。
つまり、国土交通省のガイドラインの内容にそった見解となっています。
ですので、状況に応じての判断になりますが、いずれにせよ、
賃貸借契約の中で、退去時の取り決めをどのように記載しておくか
が重要になります。
また、契約書の一般条項に記載されている事項より、
「特約条項」の箇所
に記載されていることが優先されます。
「普通借家契約」と「定期借家契約」

賃貸契約の種類としては、
「普通借家契約」と「定期借家契約」
があります。
主な違いは、
「定期借家契約」
のほうが、
オーナー(貸主)に都合が良い契約の種類
となっていると言えます。
「貸主に都合が良い」という意味合いとしては、「普通借家契約」との比較でいうと、下記になります。
細かいお話しになりますが、普通借家契約は、
期間の定めのある契約
と
期間の定めのない契約(1年未満の契約)
に分かれます。
また、「期間の定めのある契約」の場合、
契約書に自動更新、合意更新の記載があり、契約満了前に、解約の申し入れがない場合
は、自動更新(合意更新)の扱いとなり、それまでと同様の契約条件(契約期間等)で、契約が更新されるということになります。
あるいは、
契約書に自動更新、合意更新の記載がなく、契約満了前に、解約の申し入れもない場合
は、契約が終了するのではなく、
「期間の定めのない契約」
という扱いに切り替わることになります。
「普通借家契約」
普通借家契約は、基本、更新されることを前提とした内容となっています。
期間の定めのある契約
特約が無い場合は、基本、オーナー(貸主)からの解約はできない。
特約で中途解約ができることを定めてもOK。
ただし、特約があっても、オーナー(貸主)からの解約申入れには正当事由が必要。
期間の定めのない契約
テナントの借主からの解約申入れはいつでも可能。
ただし、オーナー(貸主)からの解約申入れには正当事由が必要。
「定期借家契約」
定期借家契約は、期間満了により終了することを前提としています。
引き続き、賃貸する場合は、改めて、契約の取り交わしを行います。
また、定期借家契約は、借地借家法第38条1項において、
「公正証書による等書面によって締結するときに限り」認められている
とされています。
ですので、定期借家契約は、必ず契約書を作成して締結する必要があります。
書面の形式としては、
住宅用の定期借家契約は、必ずしも公正証書による必要はない
となっていますが、
事業用の定期借家契約は、必ず公正証書によって作成する必要がある
とされてますので、注意が必要です。
また、契約の終了に関しては、細かいお話しになりますが、借地借家法38条4項ただし書では、
期間が1年以上の契約で、オーナー(貸主)が、期間満了による契約終了する際は、「期間満了の1年前から6ヶ月前まで」の間に「期間満了により終了する旨の通知」をしないと、賃貸借契約の終了をテナントの借主に対抗できない
借地借家法38条4項ただし書
となっています。
つまり、上記の通知がないと、契約の満了後、立ち退きを主張できないことになります。
但し、通知忘れした場合でも、通知後、6カ月後には、終了を賃借人に主張できるようになります。
定期借家契約においては、
中途解約の特約が有る場合
と、
中途解約の特約が無い場合
があります。
中途解約の特約が有る場合
オーナー(貸主)およびテナントの借主は、中途解約の特約に従って解約を行うことができます。
事業用の場合は、通常、3~6ヶ月前の通知が必要とされます。
また、オーナー(貸主)からの解約申入れには、6ヶ月以上の予告期間が必要と考えられ(借地借家法第27条、第30条)、正当事由もが必要(借地借家法第28条、第30条)とされます。
中途解約の特約が無い場合
事業用の賃貸借の場合は、原則として、オーナー(貸主)、テナントの借主ともに自らの都合による解約はできないとされます。
【参考】
定期借家契約が、居住用の場合は、中途解約の特約が無い場合でも、下記条件の場合は、中途解約ができるとされています。
・居住用建物の賃貸借で、契約対象床面積が200㎡未満の場合
かつ、
・やむをえない事情(転勤、療養、親族の介護等)により、テナントが賃借建物を自己の生活の本拠として使用するのが困難となった場合
つまり、
「定期借家契約」の場合は、
契約満了により、契約を終了
させることができるが、
「普通借家契約」の場合は、
特約があったとしても、貸主からの解約申入れには正当事由が必要
となります。
ですので、オーナー(貸主)としては、将来的に、オーナー(貸主)都合で契約終了する可能性がある場合は、
「定期借家契約」
を選択することになります。
まとめ

テナントを借りる際には、
賃貸借契約
に記載している
条件
を十分にチェックしておく必要があります。
そうしないと、
解約時、退去時
にトラブルに発展するリスクを内在することになってしまいます。
少なくとも、
借主側のリスクがないか
を細かくチェックすることが大切です。
以上、テナント契約時の4つの注意点についてでした。