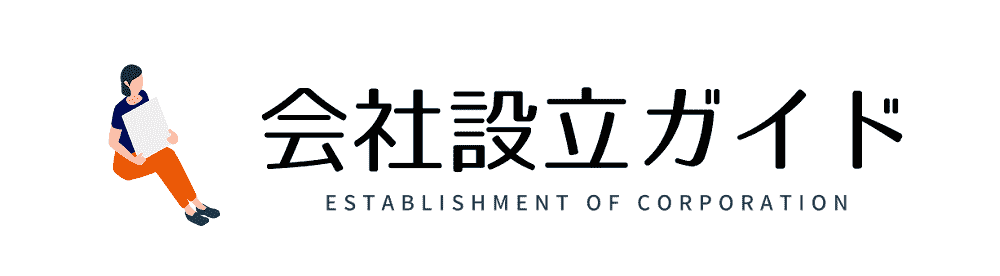会社設立で、
合同会社にするかどうか?
を検討している、注意点があれば知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
法人を設立する際、合同会社にした場合の注意点について、わかりやすく整理しています。


会社設立で、
合同会社にするかどうか?
を検討している、注意点があれば知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
会社の形態としては、
株式会社
合同会社
合資会社
合名会社
の4つがあります。
このうち、新たに法人を設立する際には、実際は、
株式会社
か
合同会社
の選択になります。
合同会社を選択されるケースは、まだ、割合的には少ないですが、
メリット
と
デメリット
がありますので、下記に整理します。
【補足】合資会社と合名会社について
老舗の酒蔵など、地元の古い会社で、
合資会社や合名会社
の場合があります。
以前は、少ない資本で設立できる法人として、この形態を選択されていたケースもありましたが、
2005年の最低資本制度の撤廃
2006年の新会社法施行で合同会社が作られた
こともあり、現在は、この形態を選択されるケースはほとんどありません。
また、
合資会社は、無限責任社員と、有限責任社員で構成、
合名会社は、無限責任社員で構成、
となっています。
無限責任社員は、会社の債務者に対する負債の責任を、個人で連帯する形となり、結果、
個人的なリスクが(個人財産に関するリスク)発生する
というデメリットがあります。
合同会社の経緯

合同会社は、
2006年(平成18年)5月1日に施行された会社法
で新たに設けられた会社形態です。
アメリカの
LLC (Limited Liability Company)
をモデルとして導入された経緯があります。
ただ、実際は、アメリカのLLCと、合同会社には、違いはあります。
【参考】米LLCの特徴
アメリカのLLCの特徴は、下記になります。
(A)出資者は自分が出資した範囲のみで責任を負う(有限責任)
(B)株式の発行はできず、メンバーが直接出資する(持分会社)
(C)メンバー自ら経営に参加するか、外部のマネージャーを任命して経営を任せることができる
(D)金銭・動産・不動産のほか役務(サービス)による出資も可能
(E)法人課税かメンバー個人の所得への課税(パススルー課税)を選べる税制面のお話しになりますが、日本の合同会社と大きく違う点として、
引用;Leagal Search https://legalsearch.jp/portal/column/limited-liability-company/
「法人課税かLLCのメンバー個人の所得への課税のどちらかを選択できる」
という特徴があります。
株式会社と合同会社の違い(定義の違い)

株式会社と合同会社の違いとしては、下記になります。
■株式会社
所有と経営の分離という考え方で、株主が会社の経営を経営者に委任し、経営者が会社の業務を行う
■合同会社
所有と経営の一致という考え方で、出資者自身が業務執行権限を有し、会社の業務を行う
「合同会社」の場合、考え方としては、従来の、「合資会社」や「合名会社」に近いものと言えます。また、「所有と経営の一致」ということは、出資者を外部から募るということはしないということです。
出資者自身が会社の業務を行います。
株式会社の場合は、
株式を発行して、出資の形式で、資金を外部調達する
ということをしますが、合同会社には、株式はありません。
ですので、その点も、合同会社の場合に注意すべき点と言えます。
もっとも、株式会社の場合でも、経営者が100%出資している場合も多くあり、実質は、所有と経営が一致しているといえるケースも多いと言えます。
合同会社に向いている業種

一般的に、
合同会社に向いている
といわれる業種があります。
内容的には、
・大きな資金調達を必要としない
・人的な資力、専門的なノウハウをもとにしたサービス
・取引先が、合同会社にこだわらない場合
・BtoBの業態、あるいは、BtoCの場合も、別の屋号で商売ができる
が向いているといわれています。
例えば、
コンサルティング業
IT関係
デザイン関係
美容院、小売店、飲食店、サロン、学習塾
不動産投資業
などの他、
個人事業からの法人成の場合
があります。
もちろん、上記以外の業種でもOKですし、また、
アップルやアマゾン
といった大企業も、合同会社の形態をとっています。
合同会社のメリット

株式会社との比較からみた合同会社のメリットとしては、下記のような事項があります。
設立にかかる費用を安く抑えることができる
法人の設立の費用に関して、株式会社よりも低く抑えることができます。
コストダウンできる項目としては、下記になります。
定款の認証料
合同会社;0円
株式会社;50,000円
登録免許税
合同会社; 60,000円(または、資本金額×0.7%のうち高いほう)
株式会社;150,000円(または、資本金額×0.7%のうち高いほう)
単純計算で、140,000円ほど、コストダウンできます。
決算公告が不要
合同会社の場合、決算公告義務がないので、その費用が発生しません。
公告の場合、通常、下記のいづれかの対応になります。
・官報(年間費用として、約7万円~)
・電子公告(年間費用として、4,000円前後~)
・自社のHP
もっとも、多くの株式会社が、決算公告をおこなっていないのが実情です。
大手の会社でも行っていないケースもあります。
役員の任期が無い
合同会社の場合、役員の任期が無いので、
株式会社の場合の任期終了後の登記の必要
もなくなり、結果、登記費用のコストが軽減できます。
株式会社の場合の役員の任期は、原則として2年で、非公開会社の場合には、取締役の任期を定款で10年まで伸長できます。
重任登記(同じ人が、引き続き役員になる場合)にかかる費用は、10,000円です。
経営の自由度が高い
利益配分に関して、株式会社の場合は、出資比率に応じた配分が必要となりますが、合同会社の場合は、そういった規制がありません。
ですので、優秀な社員の利益配分比率を高く設定するなど、その自由度が高いと言えます。
意思決定のスピード感が早い
株主会社の場合は、重要な事項を決定するために株主総会を開催する必要がありますが、合同会社の場合は、その必要がありません。
その分、意思決定のスピードが早くなります。
合同会社のデメリット

知名度、認知度が低い
合同会社の形態の会社の割合が少ない為、対外的な認知度が低く、結果、信頼度にも影響する可能性があります。
もっとも、そういった点に配慮する必要のないケースもありますので、状況に応じての判断にはなります。
個人的な見解としては、
合同会社
というネーミングが、別の名称であれば、状況も変わっていたようにも感じます。
なんとなく、文字だけからの印象では、
仲間同士で運営している小さな会社
のような感じがしますね。
資金調達の方法が限られる
合同会社の場合、株式会社のように、
株式を発行して資金調達する
ということができません。
ですので、自己資金や金融機関からの融資がメインとなります。
もっとも、社債を発行することはできますが、社債の場合、財務諸表では、
負債
という扱いになります。
社員同士が対立する可能性がある
合同会社の場合、
出資者が1人
の場合と、
出資者が複数の場合
があります。
複数の場合は、出資者である社員が、一人一票の議決権を持って意思決定を行うことになります。
その場合、
意見の対立が起こる可能性
があります。
また、下記項目の議決にも、制約があります。
・代表社員の継承、事業継承、出資者の権利譲渡
→「社員全員の同意」
・経営に関する事項
→「社員の過半数の同意」または、「は業務執行社員の過半数の同意」
社員(出資者という意味での社員)が、経営参加できるというメリットがある反面、上記にように、意見の対立が発生した際には、揉める可能性もでてきます。
もっとも、出資者が1人の場合は、そういったリスクはありません。
上場できない
合同会社の場合は、上場できないという制約があります。
形態上、株式が発行できないので、当然ですね。
その場合は、株式会社へ変更してからの上場ということになります。
まとめ

合同会社には、上記に記載したような
メリット、デメリット
がありますので、結論としては、
状況によっての判断
にはなります。
その際に、取引先など、外部に対してデメリットがないかもチェックする必要があります。
合同会社にすることによって、売上げに影響があるようであれば、検討の余地があると言えます。
また、将来的に株式会社に移行する可能性があるのであれば、移行に関する諸々のコストと手間を考えると、最初から株式会社にしておくという選択肢もあります。
以上、合同会社についての説明でした。